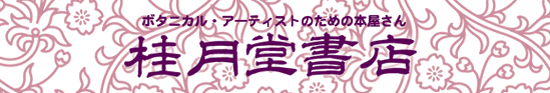FrontPage
ようこそ!
ようこそ、ボタニカルアートサロンへ。
当サイトは画家でありデザイナーでもある
吉田桂子先生が主催する、ボタニカルアートを描く人のために
情報を発信するサイトです。English Version
吉田桂子先生のボタニカルアート作品がグッズになりました。
ご興味のある方はどうぞご覧ください。
吉田桂子先生の作品をグッズで購入できるネットショップはこちらをクリックして下さい。
→Botanical art salon The goods shop
コンテンツ更新情報
- 2026.02.28 今月のタイトル花を更新しました。
- 2026.01.13 今月のタイトル花を更新しました。
- 2025.12.14 今月のタイトル花(11月、12月)を更新しました。
- 2025.11.23 今月のタイトル花(10月)を更新しました。
- 2025.09.13 今月のタイトル花を更新しました。
- 2025.08.19 今月のタイトル花(8月)を更新しました。
- 2025.08.19 今月のタイトル花(7月)を更新しました。
- 2025.06.22 今月のタイトル花を更新しました。
- 2025.04.03 今月のタイトル花を更新しました。
- 2025.03.23 今月のタイトル花を更新しました。
- 2025.02.27 今月のタイトル花を更新しました。
- 2025.01.13 今月のタイトル花を更新しました。
- 2024.12.30 今月のタイトル花を更新しました。
- 2024.11.10 今月のタイトル花を(11月)を更新しました。
- 2024.11.10 今月のタイトル花(10月)を更新しました。
- 2024.09.07 今月のタイトル花(9月)を更新しました。
- 2024.09.07 今月のタイトル花(8月)を更新しました。
- 2024.07.28 今月のタイトル花を更新しました。
- 2024.06.24 今月のタイトル花を更新しました。
- 2024.05.31 今月のタイトル花を更新しました。
- 2024.04.21 今月のタイトル花を更新しました。
- 2024.03.25 今月のタイトル花を更新しました。
- 2024.02.27 今月のタイトル花を更新しました。
- 2024.01.28 今月のタイトル花を更新しました。
- 2023.12.23 今月のタイトル花を更新しました。
- 2023.11.19 今月のタイトル花を更新しました。
- 2023.10.08 今月のタイトル花を更新しました。
- 2023.09.24 今月のタイトル花を更新しました。
- 2023.08.06 今月のタイトル花を更新しました。
- 2023.06.28 今月のタイトル花を更新しました。
- 2023.05.29 今月のタイトル花を更新しました。
- 2023.04.17 今月のタイトル花を更新しました。
- 2023.03.25 今月のタイトル花を更新しました。
- 2023.02.19 今月のタイトル花を更新しました。
- 2023.01.28 タイトル花アーカイブに2022年タイトル花を追加しました。
- 2023.01.28 今月のタイトル花を更新しました。
- 2022.12.25 今月のタイトル花を更新しました。
- 2022.11.20 今月のタイトル花を更新しました。
- 2022.10.15 今月のタイトル花を更新しました。
- 2022.09.04 今月のタイトル花を更新しました。
- 2022.08.07 今月のタイトル花を更新しました。
- 2022.07.02 今月のタイトル花を更新しました。
- 2022.06.19 今月のタイトル花を更新しました。
- 2022.05.08 今月のタイトル花を更新しました。
- 2022.04.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2022.03.15 今月のタイトル花を更新しました。
- 2022.02.07 今月のタイトル花を更新しました。
- 2022.01.06 今月のタイトル花を更新しました。
- 2021.12.05 今月のタイトル花を更新しました。
- 2021.11.13 今月のタイトル花を更新しました。
- 2021.10.21 今月のタイトル花を更新しました。
- 2021.09.05 今月のタイトル花を更新しました。
- 2021.08.17 今月のタイトル花を更新しました。
- 2021.07.03 今月のタイトル花を更新しました。
- 2021.06.12 今月のタイトル花を更新しました。
- 2021.05.03 今月のタイトル花を更新しました。
- 2021.04.04 今月のタイトル花を更新しました。
- 2021.03.06 今月のタイトル花を更新しました。
- 2021.02.06 今月のタイトル花を更新しました。
- 2021.01.23 タイトル花アーカイブに2020年タイトル花を追加しました。
- 2021.01.23 今月のタイトル花を更新しました。
- 2020.12.11 今月のタイトル花を更新しました。
- 2020.11.07 今月のタイトル花を更新しました。
- 2020.10.17 今月のタイトル花を更新しました。
- 2020.09.05 今月のタイトル花を更新しました。
- 2020.08.09 今月のタイトル花を更新しました。
- 2020.07.04 今月のタイトル花を更新しました。
- 2020.06.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2020.05.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2020.04.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2020.03.11 今月のタイトル花を更新しました。
- 2020.02.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2020.01.14 今月のタイトル花を更新しました。
- 2019.12.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2019.11.03 今月のタイトル花を更新しました。
- 2019.10.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2019.9.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2019.8.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2019.7.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2019.6.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2019.5.04 今月のタイトル花を更新しました。
- 2019.4.07 今月のタイトル花を更新しました。
- 2019.3.09 今月のタイトル花を更新しました。
- 2019.2.21 植物画ウェブ講座ページに第45回ーレンテンローズブーケを描くを掲載しました。
- 2019.1.31 今月のタイトル花を更新しました。
- 2019.1.05 今月のタイトル花を更新しました。
- 2018.12.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2018.11.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2018.10.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2018.9.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2018.8.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2018.7.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2018.6.24 植物画ウェブ講座ページに第44回ーガーベラを描くを掲載しました。
- 2018.6.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2018.5.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2018.4.27 植物画ウェブ講座ページに第43回ージャーマンアイリスを描くを掲載しました。
- 2018.4.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2018.3.21 植物画ウェブ講座ページに第42回ーカタクリの群落を描くを掲載しました。
- 2018.3.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2018.2.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2018.1.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2017.12.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2017.11.22 植物画ウェブ講座ページに第41回ーブドウを描くを掲載しました。
- 2017.11.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2017.10.27 植物画ウェブ講座ページに第40回ーハクサンシャジンを描くー彩色編を掲載しました。
- 2017.10.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2017.9.23 植物画ウェブ講座ページに第39回ーハクサンシャジンを描くーデッサン編を掲載しました。
- 2017.9.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2017.8.23 植物画ウェブ講座ページに第38回ーバラを描くー個体の描き分けを掲載しました。
- 2017.8.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2017.7.21 植物画ウェブ講座ページに第37回ーアンスリウムを描くを掲載しました。
- 2017.7.09 Botanical art salon The goods shopのオープンのお知らせ
吉田桂子先生のボタニカルアート作品がグッズになりました。 - 2017.7.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2017.6.25 植物画ウェブ講座ページに特別講義ー礼文島の花々を掲載しました。
- 2017.6.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2017.5.21 植物画ウェブ講座ページに第36回ーミヤマオダマキを描くを掲載しました。
- 2017.5.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2017.4.16 植物画ウェブ講座ページに第35回ーアイスランドポピーを描くを掲載しました。
- 2017.4.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2017.3.17 植物画ウェブ講座ページに第34回ーキバナカタクリを描くを掲載しました。
- 2017.3.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2017.2.19 道具と書籍のご紹介ページにパレットのお掃除3つの理由を掲載しました。
- 2017.2.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2017.1.28 植物画ウェブ講座ページに第33回ークリスマスローズを描くを掲載しました。
- 2017.1.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2016.12.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2016.11.25 植物画ウェブ講座ページに第32回ープリムラを描くを掲載しました。
- 2016.11.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2016.10.30 植物画家的-旅ナビページにFloraJaponica展~英国KewGardens 2016年9月25日~10月1日 を掲載しました。
- 2016.10.03 今月のタイトル花を更新しました。
- 2016.09.23 植物画ウェブ講座ページに第31回ーヒペリカムを描くを掲載しました。
- 2016.09.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2016.08.28 植物画ウェブ講座ページに第30回ートルコギキョウを描くを掲載しました。
- 2016.08.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2016.07.29 植物画ウェブ講座ページに第29回ーキキョウを描くを掲載しました。
- 2016.07.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2016.06.19 植物画ウェブ講座ページに第28回ーペチュニアを描くを掲載しました。
- 2016.06.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2016.05.22 ブログ花のある生活ページに吉田桂子展の動画をアップしました。
- 2016.05.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2016.04.23 植物画ウェブ講座ページに特別講義ームラなく塗る平塗り技法を掲載しました。
- 2016.04.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2016.03.18 植物画ウェブ講座ページに第27回ーキクザキイチゲを描くを掲載しました。
- 2016.03.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2016.02.21 植物画ウェブ講座ページに第26回ーパフィオペディルムを描くー2掲載しました。
- 2016.02.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2016.01.29 植物画ウェブ講座ページに第25回ーパフィオペディルムを描くを掲載しました。
- 2016.0101 今月のタイトル花を更新しました。
- 2015.12.30 植物画ウェブ講座ページに第24回ーカトレアを描くを掲載しました。
- 2015.12.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2015.11.13 植物画ウェブ講座ページに第23回ーデンマークカクタスを描くを掲載しました。
- 2015.11.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2015.10.11 植物画ウェブ講座ページに第22回ースカビオサを描くを掲載しました。
- 2015.10.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2015.9.18 植物画ウェブ講座ページに第21回ーナデシコを描くを掲載しました。
- 2015.9.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2015.8.23 植物画ウェブ講座ページに第20回ーダリアを描くを掲載しました。
- 2015.8.02 植物画家的-旅ナビページに伝統の朝顔展~くらしの植物苑 2015年7月30日を掲載しました。
- 2015.8.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2015.7.09 植物画ウェブ講座ページに第19回ーハイビスカスを描くを掲載しました。
- 2015.7.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2015.6.21 植物画家的-旅ナビページにフラワーセンター大船植物園~2015年6月18日を掲載しました。
- 2015.6.11 植物画ウェブ講座ページに第18回ーゼラニウムを描くを掲載しました。
- 2015.6.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2015.5.22 植物画家的-旅ナビページにローズガーデン訪問記~2015年5月14日~15日を掲載しました。
- 2015.5.10 植物画ウェブ講座ページに第17回ークレマチスを描くを掲載しました。
- 2015.5.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2015.4.29 植物画家的-旅ナビページに筑波実験植物園 2015年4月18日を掲載しました。
- 2015.4.09 植物画ウェブ講座ページに第16回ーセントポーリアを描くを掲載しました。
- 2015.4.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2015.3.26 植物画家的-旅ナビページに夢の島熱帯植物館 2015年3月20日を掲載しました。
- 2015.3.13 植物画ウェブ講座ページに第15回ーブーケを描くを掲載しました。
- 2015.3.01 今月のタイトル花を更新しました。
- 2015.2.27 特別講義ールドゥーテに学ぶ現代ボタニカル・アートの方向性 第2回を掲載しました。
- 2015.2.08 植物画ウェブ講座ページに第14回ーパンジーを描くを掲載しました。
- 2015.2.01 今月のタイトル花を更新致しました。
- 2015.1.31 特別講義ールドゥーテに学ぶ現代ボタニカル・アートの方向性 第1回を掲載しました。
- 2015.1.11 植物画ウェブ講座ページに第13回ースイセンを描くを掲載しました。
- 2015.1.1 今月のタイトル花を更新致しました。
- 2014.12.23 道具と書籍のご紹介ページに「ボタニカル・アーティストのための紙選び」を掲載しました。
- 2014.12.12 植物画ウェブ講座ページに第12回ー日常の中で楽しむボタニカル・アートを掲載しました。
- 2014.12.01 今月のタイトル花を更新致しました。
- 2014.11.16 植物画ウェブ講座ページに第11回ークヌギを描くを掲載しました。
- 2014.11.09 植物画家的-旅ナビに「富士花鳥園 2014年10月31日」を掲載致しました。
- 2014.11.01 今月のタイトル花を更新致しました。
- 2014.10.23 植物画ウェブ講座ページに第10回ーフクシアを描くを掲載しました。
- 2014.10.17 植物画ウェブ講座ページに特別講義ーボタニカル・アーティストのための色彩学を掲載しました。
- 2014.10.01 今月のタイトル花を更新致しました。
- 2014.9.21 植物画ウェブ講座ページに第9回ーハナミズキを描くを掲載しました。
- 2014.9.15 道具と書籍のご紹介ページに「額装に差が出るマットの役割3選」を掲載しました。
- 2014.9.01 今月のタイトル花を更新致しました。
- 2014.8.29 植物画ウェブ講座ページに特別講義ーボタニカル・アーティストのための色彩学を掲載しました。
- 2014.8.10 植物画ウェブ講座ページに第8回ーリンドウを描くを掲載しました。
- 2014.8.01 今月のタイトル花を更新致しました。
- 2014.7.25 植物画家的-旅ナビに「北海道 礼文島 2」を掲載しました。
- 2014.7.13 植物画ウェブ講座ページに第7回ー植物群を屋外で描くを掲載しました。
- 2014.7.01 今月のタイトル花を更新致しました。
- 2014.6.19 植物画ウェブ講座ページに第6回ースカシユリを描くを掲載しました。
- 2014.6.14 道具と書籍のご紹介ページに「もう迷わない。筆選びの3原則」を掲載しました。
- 2014.6.01 今月のタイトル花を更新致しました。
- 2014.5.11 植物画ウェブ講座ページに第5回ーアジサイを描くを掲載しました。
- 2014.5.01 今月のタイトル花を更新致しました。
- 2014.4.23 植物画ウェブ講座ページに第4回ーチューリップを描くを掲載しました。
- 2014.4.13 植物画家的-旅ナビページに「南米の不思議な果実~西川農園訪問記」を掲載しました。
- 2014.4.01 今月のタイトル花を更新致しました。
- 2014.3.22 植物画ウェブ講座ページに第3回ーツバキを描くを掲載しました。
- 2014.3.08 道具と書籍のご紹介ページに羽ぼうきの話を掲載しました。
- 2014.3.01 今月のタイトル花を更新致しました。
- 2014.2.22 道具と書籍のご紹介ページに消しゴムと練り消しゴムの話を掲載しました。
- 2014.2.08 植物画ウェブ講座ページに第2回ーバラを描く彩色編を掲載しました。
- 2014.1.31 道具と書籍のご紹介ページにカッターナイフと研芯器の話を掲載しました。
- 2014.1.12 新しく植物画ウェブ講座ページを開設致しました。このページでは、四季を彩る様々な植物の描き方のポイントを吉田先生に解説して頂きます。第1回はボタニカルアートを学ぶ方々なら誰でも挑戦したいモチーフ「バラ」のデッサン編です。どうぞご覧ください。
- 2014.1.1 2013年タイトル花の記事をタイトル花アーカイブにまとめました。
- 2013.12.21 植物画家的-旅ナビページに「鎌倉文学館と晩秋のバラ園」を掲載しました。
- 2013.12.01 今月のタイトル花を更新致しました。
- 2013.11.24 作品のご紹介ページに「名言とともに贈る~ブーケ画集」を掲載しました。
- 2013.11.06 植物画家的-旅ナビページに「岩手県大迫町」を掲載しました。
- 2013.11.01 今月のタイトル花を更新致しました。
- 2013.10.14 道具と書籍のご紹介ページに鉛筆と鉛筆ホルダーの話を掲載しました。
- 2013.10.1 今月のタイトル花を更新致しました。
- 2013.9.24 ボタニカルアートとはのページにボタニカルアートの応用編としてイチゴジャムのラベル制作の過程をアップ致しました。
- 2013.9.16 植物画家的-旅ナビページに「町田ダリア園」を掲載しました。
- 2013.9.1 今月のタイトル花を更新致しました。
- 2013.8.15 教室のご紹介ページに東京農業大学グリーンアカデミーの情報を追加致しました。
- 2013.8.15 道具と書籍のご紹介ページに吉田桂子作品集のご案内を掲載致しました。
- 2013.8.13 植物画家的-旅ナビページに「箱根探美行」を掲載しました。
- 2013.8.6 道具と書籍のご紹介ページに「植物画のためのカメラえらびと撮影術」を掲載しました。
- 2013.8.5 教室のご紹介ページに日本園芸協会さんのリンクを掲載しました。
- 2013.8.1 今月のタイトル花を更新致しました。
- 2013.7.14 道具と書籍のご紹介ページに「植物画家の本棚」を掲載しました。 吉田先生の蔵書を順次ご紹介していくページです。ボタニカル・アートを描くうえで参考になる書籍を集めています。どうぞ、ご活用下さい。
- 2013.7.08 植物画家的-旅ナビ 北海道 礼文島 1 を掲載しました。
吉田桂子 略歴
横浜生まれ
多摩美術大学卒
大手アパレルメーカーに服飾デザイナーとして勤務の後、画家として独立
英国王立園芸協会(RHS)ゴールドメダリスト
日本ボタニカルアート協会代表
2月のタイトル花

とにかく昔は沢山のラン科の植物を描いた。
これはパフィオぺディラム・プリムリナ(黄)とピノッキオ(桃)である。ピノッキオはグラコフィラムとプリムリナムの交配種なのである意味、親子の共演と言ったところでしょうか......
どちらもパフィオにしては小ぶりで可愛らしい花を咲かせます。
花の株に蕾が描かれていますが、両品種ともに花がいったん咲き終わると、下からまた花が出てきます。特にピノッキオは優秀で」3~4輪は普通に咲いていました。
近年、蘭展には足を運ばなくなってしまいました。
ある時から心を動かすような花に出会えなくなってしまったからです。
蘭工場で作られたような美しい蘭には興味を持つことが出来ないからかもしれません。でも「なんかまた蘭を描きたいなあ......」と思う今日この頃です。
画:パフィオペディルム プリムリナ&ピノッキオ
文:吉田 桂子
1月のタイトル花

このランはEpi.parkinsonianum var.falcatumという長い学名がついています。私が描いた個体は株分けしたものなのか......若い株なのか......少し小さく花も一輪しか咲いていません。この十数年後、生徒さんが大株で、たわわに花を咲かせている個体を描いていました。花の一つ一つは少し小ぶりではありますが、沢山の花を咲かせている株はそれはそれは豪華絢爛でした。しかしながら、カトレアやファレノプシスなどとは違った豪華さに感じるのは、学名からもわかるように、このランが原種系であるからかもしれません。余談にはなりますが、学名を読むとき、例えばこのランの場合、Epi.はエピデンドラム属の略号で、parkinsoniarumは種小名となります。この表記の頭文字が小文字の場合は原種であるという意味です。そしてvar.はバリアンテの略で変種の意味でfalcatumが変種名となります。学名は私のような画家にはあまり関係ありませんが、正しく観察をする助けとなる事があるのでしっかりと知っていると役に立つことがあるかと思います。
絵:ラン Epi.parkinsonianum var.falcatum
文:吉田 桂子